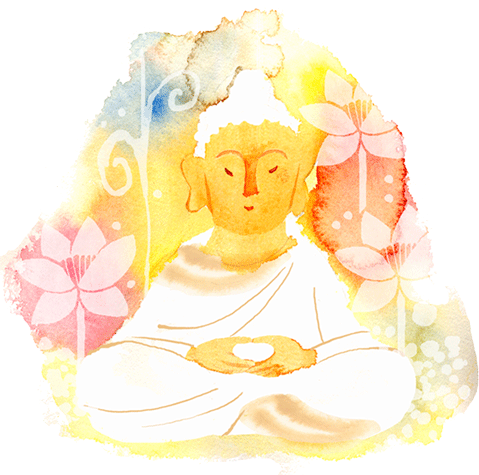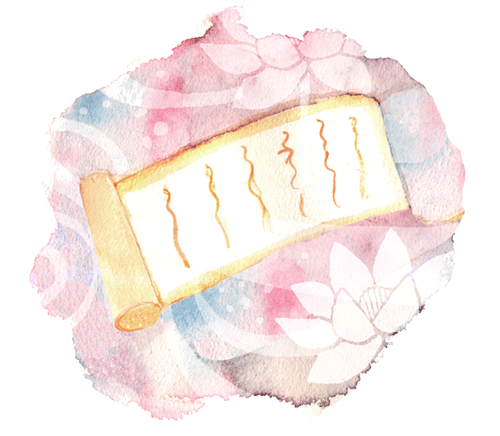●命をささげる御供養
事理供養御書
【じりくようごしょ】
今回取り上げる『事理供養御書』という書状は後半が紛失しており、書かれた年次や宛先が不明です。年次については建治(けんじ)2年〈1276〉と推定されていますが、誰に向けてのお手紙だったのかはいまだ分かっていません。名も知らぬ檀信徒に向けてのお手紙ということですが、きわめて重要な教えが書かれています。
本書は、日蓮聖人が白米・毛芋・河海苔などの食べ物を贈呈された、すなわち「御供養」されたことに対してお書きになったお礼状です。こうしていただいた食べ物は、いわば命という灯火を燃やすための灯油にあたる。灯油が尽きれば灯火は消えるように、食べ物がなくなれば命は絶えてしまう……と本書ではいわれています。
その「命」というものは、あらゆるすべての財宝の中でも第一の宝である〈いのちと申物(もうすもの)は一切の財(たから)の中に第一の財なり〉。たとえこの全宇宙を財宝で満たしても、命に換えることはできない。したがって、最も価値のある宝である命を捧げるのが、一番の「御供養」になる。これを漢語では「帰命(きみょう)」といい、天竺〈インド〉の言葉では「南無」(Namas)という……こうして「南無妙法蓮華経」の「南無」の意味が説かれています。
それゆえ昔の聖人たちは、自分の命を仏に捧げて成仏した、として『涅槃経(ねはんぎょう)』に出る雪山童子(せっせんどうじ)の故事や、『妙法蓮華経』〈以下『法華経』と略記〉に出る薬王菩薩(やくおうぼさつ)の逸話などが引かれます。雪山童子は、仏法について知っているという鬼〈羅刹(らせつ)〉から教えを授かったお礼に、自分の肉体を食糧として差し出したという修行者です〈実は、お釈迦様の前世です〉。薬王菩薩は『法華経』薬王菩薩本事品(やくおうぼさつほんじほん)第二十三に出る菩薩で、自らの両肘を燃やすことによって仏に「燈明供養(とうみょうくよう)」を捧げた、といわれます。いずれも壮絶な、まさに「命がけの」御供養です。
しかし、こうした聖人たちのような壮絶な御供養は、私たちのような平凡な人間〈凡夫(ぼんぶ)〉にできるはずもありません。そこで凡夫は「志」という字を心得て成仏する、と本書は説いています。「志〈こころざし〉」とは「観心(かんじん)」、つまり「心をくんで見る」ということです。「命を捧げる」という心をくんで、できるかぎりの供養をすればいい、ということです。それは具体的にいえば、食べ物を御供養することである、と本書は述べています。
先にも見たように、食べ物とは〈まるで灯油が灯火を点すように〉命をつなぐものです。この悪世にあって、貴重な食糧を御供養することは、命を仏に献上することに他ならない……。したがって食べ物を供養する功徳は、薬王菩薩が肘を焼き、雪山童子が我が身を鬼に食べさせようとした功徳(くどく)に勝るとも劣らない、といわれています。
薬王菩薩や雪山童子のような聖人たちが実際に命を捧げた御供養は「事供養」〈事実として行なわれた供養〉、「命を捧げる」という心をくんで凡夫が行なう御供養は「理供養」〈道理にもとづく供養〉と言い分けられます。しかし、この「事供養」と「理供養」〈これが本書の題に冠された「事理供養」〉は完全に一致し、世間に事実としてある法〈事法〉となります。それが真実の仏道です。つまり薬王菩薩や雪山童子がなしたような「命を捧げる行」が、「食べ物を供養する」という形で世間では行われるわけです。まさに日蓮聖人に対する白米の御供養は、これに当たります。
こうして日常的に行われる白米の御供養などを「命を捧げる行」として認めるように、「世間に実際にあることが、そのまま仏教のすべてである〈世間の法が仏法の全体〉」と言い切るのが『法華経』の本意です。しかし、そこまで言い切れない通常の仏教経典は、世間に実際にあることを仏教に「ことよせて」説こうとするにとどまります。つまり「月のように澄んだ心である」「花のように清らかな心である」というような説き方をしています。
これに対し『法華経』は「月こそが心そのものだ」「花こそが心そのものだ」という言い方をします。そのため、『あなたがくださった白米は「命のような白米」どころではなく「命そのもの」なのだ。あなたは命を捧げる御供養をなさったのだ』と本書は決しています〈白米は白米にはあらず。すなはち命なり〉。
このように日蓮聖人は「仏道のため命を賭けよ」と激励しつつ、その具体的な方法としては、凡夫が日常の中で行える実践を示しておられます。そしてそれをもって、名も伝わらぬ檀信徒に対し、厚い感謝の思いを綴っておられるのです。この思いを受け止めて、私たちも「世間の法が仏法の全体」という『法華経』の本意にしたがい、生活の中で仏道を実践していきたいものです。